中医学・漢方– category –
相模原 タナココ漢方薬局・鍼灸接骨院 & よもぎ蒸しサロン・カフェでは妊活(不妊治療)をはじめとした様々なお悩み・不調に薬剤師・鍼灸師・柔道整復師・看護師・保育士・リラクゼーションセラピストなどの専門家が対応いたします。
お気軽にお問い合わせください。
-

日本の働く人と「こころ」のリアル
メンタルヘルスが仕事や社会に与える「見えないコスト」とは? -

どの野菜を選ぶかで、体の調子がこんなに変わる!
カラダの内側から守る!◯◯科野菜の新・健康パワー! -

アイデアは歩いて生まれる!
仕事・勉強・日常の発想力を自然に高めるウォーキングの力! -

赤ワイン神話の崩壊…?
「1日1杯で健康」は本当か?アメリカ心臓協会の最新見解。 -

叫べば強くなる!?〜「孫悟空」の雄叫びの秘密に迫る〜
スポーツパフォーマンスを高める意外な方法とは? -

夜ふかしと寝不足と血糖値
「寝る時間」と「睡眠の長さ」が血糖値にどう影響するかを、最新の医学研究と中医学の視点からわかりやすく紹介 -
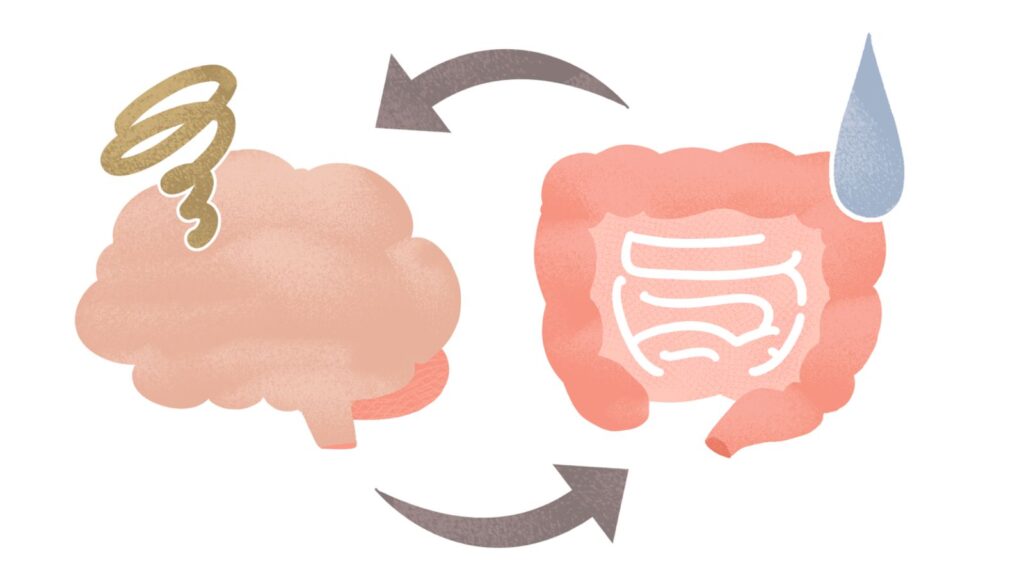
「ストレスに強い腸内細菌」が心を守る
レジリエンスを高める腸内細菌の働きを科学的に解説します。 -
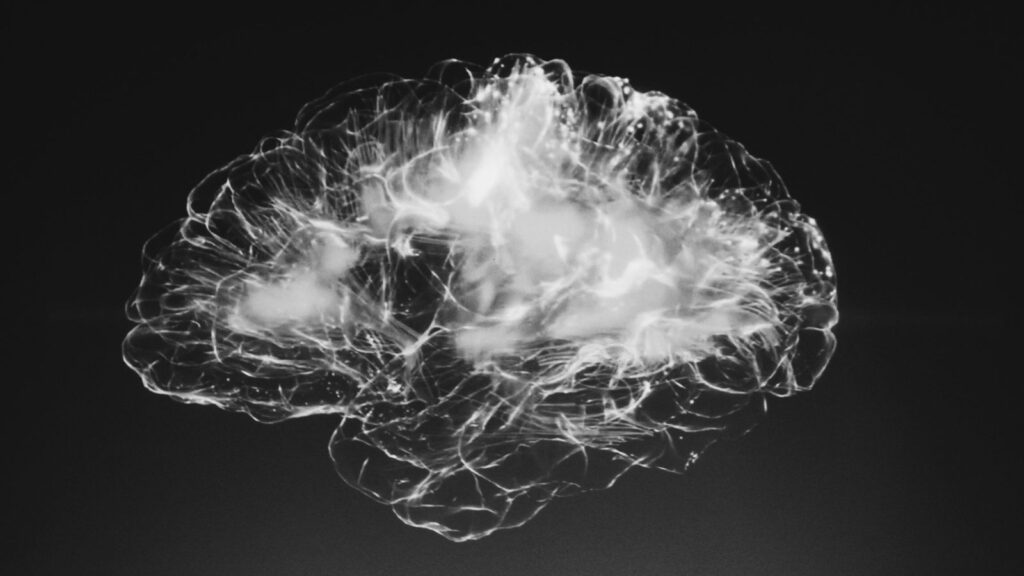
「認知症」になる前に脳が出す「SOS」とは?
fMRIとAIを使った認知症リスクの予測研究についてです。 -

「やさしさ」は健康の万能薬? 科学が証明した「人に優しくする」ことのすごいパワー
やさしさが心と体を整える。最新研究が示す「向社会性」の驚くべき健康効果とは。 -

「体によさそう」が本当にそうとは限らない
高塩食品の摂取が口腔がん、咽頭がん、そして食道がんのリスクとどう関係しているかを明らかにした研究があります。
